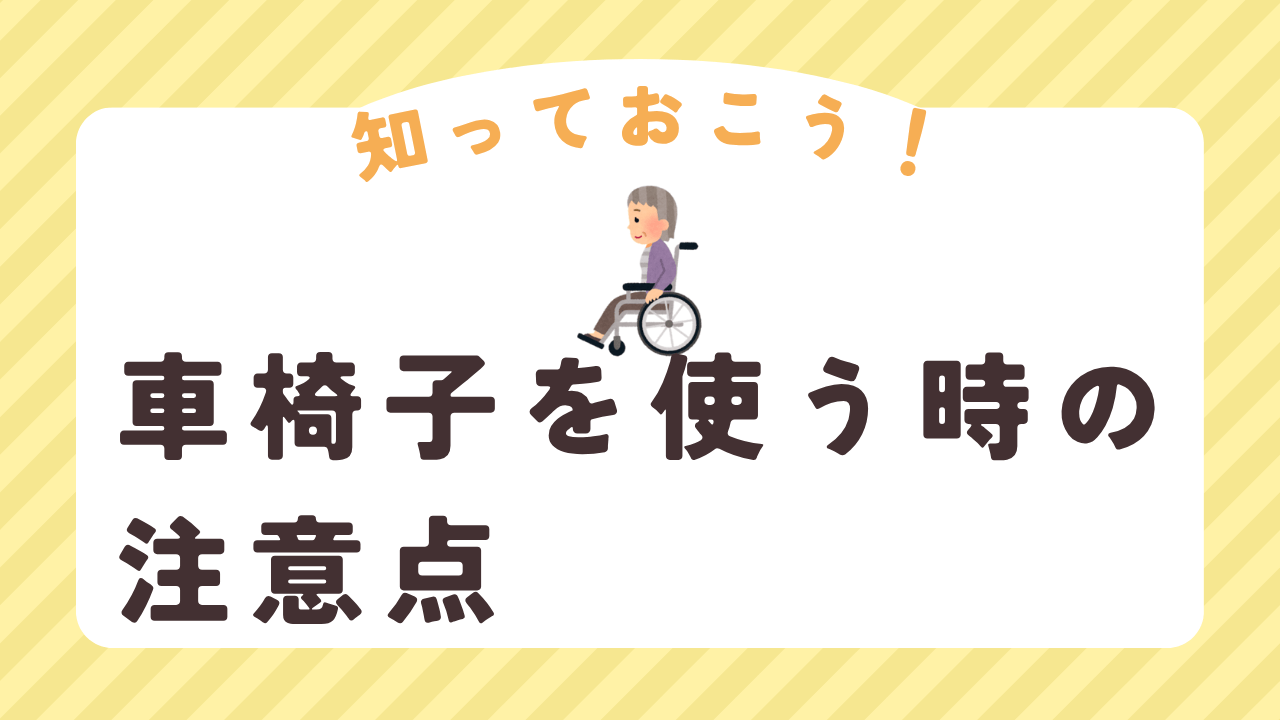理学療法士として病院や施設で勤めていく中で、車椅子を使うにあたって、『これはいい』『こういう失敗をする方が多いから気を付けた方がいい』ということがいくつかありました。
病院勤めの方なら知っている車椅子に乗る時の注意点、プチアドバイスを一般の方向けに簡単に紹介します。
通常の使い方についてはいろんなサイトに載ってると思うのでそちらを参考にしてください。
①車椅子は手でこぐ 足は舵取り
②タイヤの空気はきちんと入れる
③軽い車椅子は引っ張ると動く
④立ち上がりにくい時は
⑤奥行が深すぎる時
⑥麻痺してる腕が肘掛けにあたっていると床ずれができる
⑦物を拾おうとすると転落する
⑧ブレーキは必ずかける
⑨立ち上がる時はフットプレートをあげる
⑩座布団を高くしすぎると横に落ちやすい
⑪車椅子で寝てしまって転落
⑫ブレーキの棒にラップの芯をさす
車椅子使用時のポイント
①車椅子は手でこぐ 足は舵取り
両手のみ、両足のみでこいでいる方は別ですが、脳梗塞など片側が麻痺している方の場合、左右どちらかだけを使ってこぐことになります。

その場合、前に進むのは手の力で、舵を取るのは足を使って行います。
たまに手を使わず足だけで進もうとする方がいますが、片足のみでこぐのはかなり大変です。
足がしっかりつかないと舵が取れないので、厚い座布団などで足が届きにくいと車椅子をこぎにくくなるので注意が必要です。
②タイヤの空気はきちんと入れる
自転車と同じなのでわかるとは思いますが、タイヤの空気が少ないと地面とタイヤの接触面積が大きくなり、こいだ時にとても重たく感じます。
また、ブレーキのかかりが悪くなるため大変危険です。
ブレーキのかかりが弱いと、乗り移りの際に後ろへ動いてしまい、転落の危険があります。
時々タイヤの空気をチェックをしましょう。
③軽い車椅子は引っ張ると動く
介助用や軽量の車いすは、折りたたんで運ぶ際などは便利ですが、乗り移りの際引っ張って立ち上がってしまうと持ち上がりやすいです。
引っ張って立たない方がいいですが、もし車椅子を引っ張ってしまうようなら、ある程度どっしりした作りの物にしましょう。
④立ち上がりにくい時は
浅く座った方が立ちやすいです。

浅く座り過ぎるのも危険ですが、立つ時には、
- 少し前に出て、浅く座り直す
- 膝をしっかり曲げて足を引く
- 体を前かがみにして足に体重をかける
これをしてから立ち上がりましょう。
また、座布団を入れて座面を高くすると立ち上がりやすいです。
ただし、座面を高くすると、足が地面につきにくくこぎにくくなることもあるため、注意してください。
⑤奥行が深すぎる時
小さいおばあちゃんだと、奥行きがありすぎて後ろに行ってしまい、足が届きにくいことがあります。
背中にクッションを入れて調節しましょう。
⑥麻痺してる腕が肘掛けにあたっていると床ずれができる
麻痺してる腕が、常に肘掛にあたってしまっていると褥瘡(床ずれ)ができます。
当たっている部分にクッションを入れましょう。
麻痺していると痛みを感じにくいので、気が付かないうちに当たっている部分が床ずれになっていたりします。
⑦物を拾おうとすると転落する
両足をしっかりついて踏ん張れる方ならまだいいのですが、脳梗塞などで片足が麻痺している方などは、物を拾おうと力を入れた際、麻痺した足が曲がって車椅子の下に入り込み、前に転落します。
自宅で転倒したって方がけっこういますので、注意してください。
車椅子の後ろが持ち上がることもあります。
⑧ブレーキは必ずかける
ブレーキをかけるのが面倒だったり、降りた後に車椅子を邪魔ではないところに移動させたいがために、ブレーキをかけずに乗り移る方がいます。
危険です。しっかりブレーキをかけましょう。
特にベッドから車椅子に移る時は確実にかけましょう。
⑨立ち上がる時はフットプレートをあげる
乗り移りの際、足を乗せる板(フットプレート)を下げたままでまたいで乗り移る方がいます。
引っかかってバランスを崩して転倒する方が多々います。
施設内では、認知症で持ちあげるのを忘れてしまう方は、フットプレート自体を外してしまったりします。
ブレーキをかけず、フットプレートもあげず、その状態で移るというのが一番危ないです。
まれにフットプレートに足を乗せたまま立ち上がろうとする方もいます。
そのまま立ち上がると車椅子が前方に傾きますので、注意してください。
⑩座布団を高くしすぎると横に落ちやすい
床ずれ防止用に厚みのある座布団を入れると思いますが、座面が上がった分、体に対して肘掛が低くなります。
不安定な方だと、横に傾いた際に落ちやすくなります。
ふだんは平気でも、車椅子に座ったまま寝てしまって体半分横に飛び出している方もいます。
⑪車椅子で寝てしまって転落
車椅子に限らないことですが、座っている時間が長く、そのまま眠てしまうと転落します。
特に麻痺している方などは、転落しそうになってハッと気がついても、踏ん張って戻すことができません。

車椅子上で眠ってしまうという方は、背もたれを倒せるリクライニング車椅子を使うか、車椅子用のテーブルを乗せるといいです。
ずり落ち防止に、股につける安全ベルトもあります(施設で使うのは身体拘束になるので現在は禁止ですが)。
⑫ブレーキの棒にラップの芯をさす
ブレーキが硬くてかけにくい方、片手が麻痺していて、麻痺してる側のブレーキを健側の手でかける方、ぜひラップの芯をブレーキの棒につけてみてください。

届きやすくもなりますし、力を加えやすくもなり、楽に動かせるようになります。
老人施設ではラップの芯に色つきのテープを巻いておしゃれにしてつけてます。